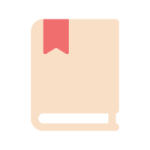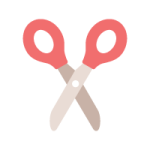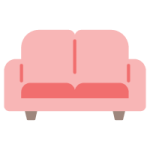自宅や園の庭、家庭菜園でもよく見かける、ミミズ。子どもにとっても、身近な存在です。でも、その生態となると、気にしたことがない、という方も多いのでは。そこで、ミミズ研究者の南谷幸雄さんに、「ミミズを親子で観察するには?」「どうしてミミズ研究者になったの?」などお話を聞きました。
重要だけど、よく知らないミミズを親子で観察しよう
ミミズは、面白い生き物ですよ。子どもでも誰でも知っているし、触ったことがある人も多い。でも、こんなに身近にいるのに、どうやって暮らしているのか、あまり知られていません。
そんなミミズですが、落ち葉や有機物の多い土壌を食べて、植物に必要な栄養素の含まれたフンを出したり、多様な動物のエサになったりと、生態系の中ではとても重要な役割を果たしています。
夏休みに親子でミミズを観察するのもいいですよ。夏から秋にかけては、野外で簡単に見つけられます。ミミズは乾燥と高温に弱いので、森の中など湿った涼しい場所で落ち葉の下を探してみてください。道路脇の側溝なども見つかりやすいですね。毒のあるミミズは見つかっていないので、素手で触っても大丈夫。ただし、土には雑菌がいるので、触った後は必ず手を洗ってください。
観察は、まずは「どっちが背中でどっちがお腹?」から始めてみましょう。同じように見えますが、黒っぽいのが背、白っぽいのが腹。次に、頭と尻尾を見分けます。皆さん、意外と「ミミズの頭はどっち?」なんて気にしたことがないのでは?腹を下にして置くと、進んでいく方が頭です(※後退もします)。ミミズには、ヘビのようにくねくね進む種類もいれば、伸び縮みして進む種類もいます。動きを観察してみましょう。床が湿っていたり、ざらざらしていたらどうするかな?自由研究にもなりそうですね。
最初は「鳥のエサ」として、いつしか「ミミズの人」に
子どもの頃からミミズが好きだったわけではなくて、もともとは動物全般、特に鳥が好きでした。父は植物や地学が好きなので、その影響もあったかもしれません。私は5人きょうだいの3番目なのですが、5人とも興味の対象が違うので、「勝手にしなさい」と親は割と自由にさせてくれました。近くの動物園は小学生から、中学生になると他県の動物園や水族館にもひとりで出かけていました。野鳥の観察会にもよく行っていましたね。
大学院に進むと、高知県の県鳥ヤイロチョウの研究に取り組みました。ヤイロチョウはミミズを食べます。ところが、どんな種類のミミズを食べているのか調べるために、採れたミミズを専門家に送ったところ「ほぼ新種だからわからない」と返ってきました。実はミミズの研究は発展途上で、まだ存在すら知られていない新種候補のミミズが日本にはたくさんいるのです。やむなく自分でミミズを研究するうち、だんだん学会でも「ミミズの人」と思われるようになり、ミミズが専門になっていきました。
わかっていることは一部だけ世界は広く、面白い
双子の娘たちは今2歳です。もうイヤイヤ期が大変で、何を言っても「イヤ!」ですね。日中は妻に任せっきりですが、毎日お風呂は入れています。娘たちにもダンゴムシを見せたりはしますが、反応は、多少は興味、くらいですかね。将来は一緒に生き物を観察できるといいな、と思っています。
子どもたちに伝えたいのは、「私たちは、見える部分のごく一部しかわかっていない」こと。教科書で勉強していると、どこかに答えがあると思いがちですが、よく調べてみるとまだ解明できていないことの方が多いことを知ってほしいですね。
保護者の皆さんも、「なぜ」「どうして」と子どもと一緒によく考え、学び、比べたり実験したりすると、発明や新発見につながるかもしれません。
栃木県立博物館テーマ展「ミミズ」
2025年11月15日(土)~2026年4月12日(日)