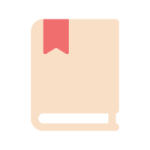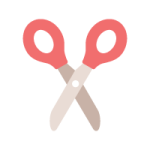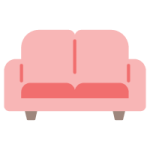ボルネオ島の熱帯雨林で、長年オランウータンの研究をしていた、久世濃子さん。そんな久世さん自身が2児のママになり、見えてきたものとは?サルの研究を通して、「ヒトの子育て」を考える連載です。
この連載では、農耕を開始する以前の社会で、ヒトがどのように暮らし、子育てしていたかを考えています。自然人類学を学んだ筆者が、自身が子育てしながら感じたことや考えたことを書いていますので、しっかりした学術的な根拠(研究論文)がない話も含まれます。「そういう考え方もあるのか~」と気楽な気持ちで読んでいただければ幸いです。
オランウータンの保護施設で行われた「遊び」の研究
今回の記事は、前回の記事(サルの子どもも木の枝で遊ぶが、「綱引き」で遊ぶのはヒトだけ【コソダテ進化論】)の続きです。
オランウータンの保護施設で行われた、「遊び」に関係する面白い研究があります。
その施設に保護されていたのは母親を殺されて孤児になった、コドモのオランウータンたちで血縁関係はなく、年齢は推定3~10歳でした。
39頭のグループでしたが、観察していると、「イノベーター(発明者)」と研究者が名付けた、次々と新しい「水遊び(行動)」を「発明」する個体がいました。
イノベーターが発明した行動(水の中に入って歩く、葉をスポンジ状にして木のウロに溜まった水を吸い取って飲む、等々)は、イノベーター以外の子どもたちにも少しずつ広がり、多くの行動はみんながするようになります。
新しいことを始める個体は決まっていて(16頭)、残りの個体(13頭)はイノベーターの行動を「観察」して、試行錯誤しながら新しい行動を身につけていました(イノベーターが積極的に「教える」ことはない)。
これはオランウータンの例ですが、おそらくヒトでも、新しい遊びを次々発明する「遊びが得意な子(イノベーター)」と「得意ではない子(ノンイノベーター)」がいて、コドモたちは集団で遊べれば、イノベーターのおかげで飽きることなく遊んでいられるのかもしれません。
でも、コドモの数が少なかったら?
イノベーターがいなくて、遊びを長続きさせるのが難しくなるかもしれません。
オモチャがなくても、「見立て」ができれば遊びは続く
個人的には、サルにとってもヒトにとっても、本当に必要なものは、「遊び友達(遊び相手)」であって、物ではないと思います。
一緒に遊ぶ仲間がいるなら、創意工夫と見立てで、オモチャがなくても楽しく遊べるし(ある程度大きくなれば;個人的には自由にひとりで歩けるぐらいの年齢だと思います)、親が遊び相手になってあげる必要もない。でも逆に、遊び仲間がいないのなら、(その代償として)オモチャを与える必要があるのかもしれません。
その子に「イノベーター」としての才能があれば(あるいはイノベーターと遊んだ経験が豊富にあれば)、ひとりでも「見立て」で楽しく遊べるかもしれません。でも、イノベーターとして遊んだ経験もほとんどなかったら?どうやって見立てて遊べばいいか、親やまわりのオトナが「イノベーター」代わりになってあげる必要があるかもしれません。
参考文献
亀井伸孝 編著(2009)「遊びの人類学」(昭和堂)
※狩猟採集民やサル(動物)の遊びの研究を紹介するエッセイ集。前回の記事(サルの子どもも木の枝で遊ぶが、「綱引き」で遊ぶのはヒトだけ【コソダテ進化論】)で触れた、私の友人も執筆しています。
※この記事は、2016年~2017年に「つくば自然育児の会」会報に連載された「パレオ育児」に加筆修正したものです。