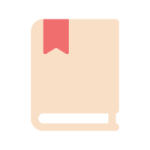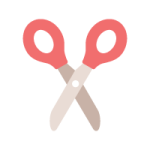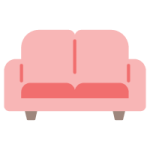早期教育を受けたという東大生は一人もいなかった
わが子を何とか優秀な子にしたい、ということで、ほんの幼いころから文字や数などの教育を始めたらいいのではないか、と早期教育に関心が向かう人がいます。
実際に、2歳、3歳から文字や数、基本的な図形問題などをさせている教室もありますし、そうした教育に熱心な保護者もいます。
でも、なるべく早くからそうした文字や数の教育を受けると頭がよくなって優秀な子になるということは、学問的には全く実証されていないのです。実際に私は東大で長く教えていましたので、東大に入ってきた学生に、早期教育を受けたことある?と何人もに聞きましたが、受けたという学生は一人もいませんでした。
私の一番上の子どもは、自分で本を読むことに興味がなく、毎日これ読んで、とたくさんの絵本を私のところに持ってきて読み聞かせをせがむ子でした。小学校に入っても、教科書を持ってきて、これ読んで、と要求してきたほどです。自分で読むより親に読んでもらうことが好きだったのです。
この子は学校で文字を習って読めるようになるとどんどん自分で本を読む子になり、6年生になったときは、成績が一番良いのは国語になっていました。わが子に関する限り、国語の成績と文字を早く読めることには直接の関係は何もないことがわかっています。関係があるのは、本を読んでもらうことが好きであること、つまり言葉の作品への興味関心が豊かにあることなのです。文字ではありません。文字は言葉を表す手段の一つにすぎないのです。
数の方は、それに比して、例えば小学校に入るまでに数唱がきちんとできること、できれば100ぐらいまで数えることが望ましいかもしれません。数唱が大事というよりは、数の世界への関心を数唱で示しているということです。お父さんの肩を100回たたく、ということを毎日するような子は、小学校で算数が苦手になることはないと思います。
大事なのは、読み聞かせや、具体的なものを数える等の、文化の世界への興味関心が豊かにあることであって、その手段である文字や数の世界に早く入ることではないのです。