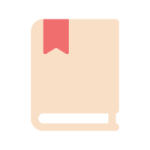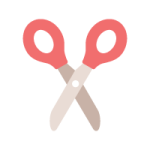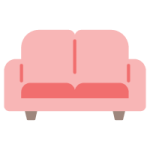ボルネオ島の熱帯雨林で、長年オランウータンの研究をしていた、久世濃子さん。そんな久世さん自身が2児のママになり、見えてきたものとは?サルの研究を通して、「ヒトの子育て」を考える連載です。
この連載では、農耕を開始する以前の社会で、ヒトがどのように暮らし、子育てしていたかを考えています。自然人類学を学んだ筆者が、自身が子育てしながら感じたことや考えたことを書いていますので、しっかりした学術的な根拠(研究論文)がない話も含まれます。「そういう考え方もあるのか~」と気楽な気持ちで読んでいただければ幸いです。
ヒトの集団のサイズは150人程度?
以前、「サルの子どもの集団規模はどのくらいですか?本来のヒトから見て、ヒトの小学生にちょうどいい集団規模は?」という質問をいただいたことがあります。
まず、生物学的な根拠に基づくヒトの集団のサイズは150人程度、といわれています(ダンバー数)。この数字はいくつもの研究によって確かめられていますが、最近はSNSの発展に伴って、この数字を否定する研究や意見も出てきています(例:https://globe.asahi.com/article/14378335)。
たとえば皆さん、SNSやLINEなどにはたくさんのお友達が登録されていると思います。私の Facebookの友達は600人以上います。でも日常的に連絡をとりあっている人、すぐに名前と性格等の個人情報が浮かぶ人は、家族や親戚も含めて数え上げると、おそらく150人前後です(「登録あるけど、この人どこで知り合った人だっけ?」みたいな人もたくさんいます)。
それから、サル(霊長類)の脳の「大脳の新皮質(言語や計画性など高度な知性を司る部位)の相対的な大きさは、その種の群れサイズと相関する」という有名な研究があります(Dunbar 1992)。小さな群れ(単独性や核家族のみ)で暮らすサルでは小さく、大きな群れ(数十頭)で生活するサルでは大きくなります。いろいろな種の相対的な大脳皮質の大きさをグラフにすると、ヒトの値はちょうど群れサイズが150頭前後の位置にプロットされます。
定住する農耕生活が始まる以前の、ヒトのもともとの生活様式である狩猟採集をしながら移動生活をしている人たちは、通常、核家族が数家族集まって「キャンプ」と呼ばれる一時的な村をつくります。核家族=両親と子ども2~3人×2~3家族=20人前後がキャンプのメンバーです。でも、核家族の組み合わせはしょっちゅう変わります(数週間~数ヵ月単位で)。ところが、長期的にみるとだいたい150人くらいが一つまとまりになっていて、その中の家族で組み合わせが変わります。また、1人が日常的につきあっている人数を数えると、150人くらいになるそうです。
同年齢の子どもたちの集団は、ヒトのもともとの生活では有り得ない
狩猟採集民の生活を見ていると「(生物としての)ヒトのもともとの集団」の「量」と「質」が見えてきます。
まず、同じ年齢の子どもたちで集団をつくること自体が、ヒトのもともとの生活を考えると、ありえないことです。なぜなら集団のサイズ(親の人数)は限られている上に、乳幼児の死亡率は高く(50%近いこともあります)、同じ年に複数の子供が生まれて一緒に成長できることはまずありません。異年齢の子どもたちで集団をつくるのが、もともとのヒトの姿だったと言われています。
狩猟採集民のキャンプに集まるのは数家族なので、自由に歩けるようになった子~未成年(10代前半ぐらいまでの子)まで、さまざまな年齢の子が一緒に連れ立って、大人とは別に行動することが多いそうです。上の子たちが下の子の面倒を見たり、下の子が上の子を真似したり、追いかけたり。そうして遊びながら、狩猟採集民として生きていく術を学びます(高田 2025)。
さらにキャンプのメンバーは流動的でしょっちゅう入れ変わります。同じ子どもたちが集団で、何年も一緒に過ごすというのは、ヒトのもともとの生活からはじつはかけ離れています。
狩猟採集の社会では、キャンプのメンバーが入れ替わる原因の一つが「仲違い」だそうです(親戚や友人に会いたくなった、行きたい方向が他のメンバーと違う、などいろいろな理由があります)。なんとなく、関係がぎくしゃくするな、と思ったら、仲直りのために多大な労力を費やすのではなく、「離れる」。これが実はヒトの人間関係の基本のようです(大人も子どもも)。
狩猟採集民は、核家族(両親+未成年の子どもたち)が基本で、3世代以上の大家族が常に一緒、という生活はしません。なので嫁姑がずっと一緒に過ごすということもほとんどありません(それでも嫁姑はやっぱりあまり仲が良くないことが多いようです)。もちろん、子どもたちは、大人になっても、両親や兄弟姉妹の一家と一緒に過ごすことは多いですが、ずっと一緒に生活するというわけではありません。
実は、このような緩い群れ生活を送るサルの中ではめずらしいのです。
たとえばニホンザルは、娘たちは母親のもと(生まれた群れ)に留まり、息子たちは群れを出ていきます。そのため、群れの雌たちは全員血縁がありますが、家族(家系)ごとに順位が決まっています。上位の家系の若い雌が、下位の家系の年上の雌を追い払ったり、攻撃しても、下位の雌は反撃することもほとんどありません。そして雌たちは、この厳しい順位関係から死ぬまで逃れることができません。
この続きは、次の連載回でお伝えします。
※この記事は、2016年~2017年に「つくば自然育児の会」会報に連載された「パレオ育児」に加筆修正したものです。
参考文献
ロビン・ダンバー著(2025)「友達の数は何人?: ダンバー数とつながりの心理学」青土社
R.I.M. Dunbar (1992) “Neocortex size as a constraint on group size in primates” Journal of Human Evolution: Volume 22, Pages 469-493
高田明(2022)「狩猟採集社会の子育て論」京都大学学術出版会