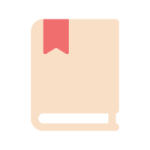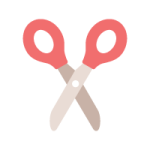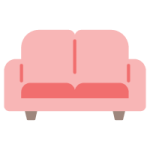ボルネオ島の熱帯雨林で、長年オランウータンの研究をしていた、久世濃子さん。そんな久世さん自身が2児のママになり、見えてきたものとは?サルの研究を通して、「ヒトの子育て」を考える連載です。
この連載では、農耕を開始する以前の社会で、ヒトがどのように暮らし、子育てしていたかを考えています。自然人類学を学んだ筆者が、自身が子育てしながら感じたことや考えたことを書いていますので、しっかりした学術的な根拠(研究論文)がない話も含まれます。「そういう考え方もあるのか~」と気楽な気持ちで読んでいただければ幸いです。
「仰向けに寝かせられる」は、サルにはない、ヒトの赤ちゃんの特徴
今回の記事は、前回の記事(「コドモから片時も離れず育児に専念する母親」は哺乳類ではとても珍しい【コソダテ進化論】)の続きです。
ヒトは、「離巣性のサルから、二次的に就巣性へと進化した、ちょっと変わった種」だと前回お伝えしました。
そして、就巣性になることで、ヒトの赤ちゃんとサルの赤ちゃんの間で、大きな違いが生まれました。ヒトの赤ちゃんは仰向けに置いても、おとなしく寝ていることができますよね?(背中スイッチとか、抱っこしないと寝てくれない赤ちゃんもいますが)
でも、サルの赤ちゃんは、仰向けに置かれると、不安そうに手足をジタバタさせて、寝るどころではなくなってしまいます(竹下 2001)。サルの赤ちゃんはお母さんの体にしがみついているのが普通で、安全な状態なので、お母さんの体から離れて、仰向けにされるというのは「異常事態」なのです。仰向けに置いたサルの赤ちゃんに、丸めた毛布やぬいぐるみを与えて、しっかり抱きつけるようにしてあげると、赤ちゃんたちは途端におとなしくなります。
「仰向けに置いておくことができる」という生物学的な特徴から、ヒトの赤ちゃんはお母さんにずっと抱っこされている必要はない、ときには置かれても大丈夫、という環境で育つのが「普通」であることがわかります。
母親の拘束下から赤ちゃんを解き放ち、他者に預けることが「ヒト本来の子育て」
サルの赤ちゃんも、お母さん以外の雌がよく抱っこして、お母さんはときどき授乳するだけ、という種が多く見られます。このように母親以外の他個体がこの世話をすることを、専門用語で「アロマザリング(共同保育):allo-mothering」といいます。
「アロマザリング」をするサルの多くには、共通した特徴があり、乳児のうちは体毛の色がオトナとまったく違います。
たとえばシルバールトンという種では、オトナはその名の通り銀灰色の体毛で全身が覆われていますが、コドモは鮮やかなオレンジ色です。雌、特にまだコドモを産んでいない若い雌たちは、このオレンジ色にひきつけられ、争うように赤ちゃんを抱っこするそうです。アカンボウ期を過ぎると、体毛はオレンジから灰色に変わり、色が変わると母親以外の雌たちが世話することはほとんどなくなります(コドモ同士で遊ぶようになります)。
「アロマザリング」は、お母さんにとって育児の負担が減る、というだけでなく、コドモにとって「集団内の多様な個体と出会い、親密な絆をつくることができる」というメリットがあります。
「しっかりと母親に守られた状態というのは子どもに安全をもたらすが、それは見方を変えれば母親の拘束下におかれているということでもある。」(根ヶ山・柏木 2010)。
ヒトは、母親がほぼ一人で子育てする類人猿から進化する過程で、父親やお祖母ちゃんはもとより群れの仲間と協力して「アロマザリング」する種として進化してきました。
新生児の頃から仰向けに置かれても機嫌良く過ごすことができるヒトの赤ちゃんは、「お母さん以外の他者」へも開かれた存在であり、優れたコミュニケーション能力を持っています(たとえば「泣くこと」も他者を自分にひきつける、コミュニケーションの手段といえます)。
生物としてのヒトの育児は、母子が巣穴にこもる「就巣性」ではなく、運動能力が劣っている赤ちゃんも母親以外の他者にも世話される、他者に開かれた存在だという点に特徴があります。母子だけが密室にこもるような「就巣性」育児ではなく、保育施設等を活用しながら、赤ちゃんが母親以外の他者とも触れあう機会を持てる、「共同保育」を実現できると、多くの親子がよりハッピーに過ごせる社会になるだろうと私は思います。
〈参考文献〉
●竹下秀子(2001年)「赤ちゃんの手とまなざし─ことばを生みだす進化の道すじ(岩波科学ライブラリー)」岩波書店
●根ヶ山光一,柏木惠子(編集)(2010)「ヒトの子育ての進化と文化– アロマザリングの役割を考える」有斐閣
●サラ・ブラファー・ハーディー(2005年)「マザー・ネイチャー(上)(下)」早川書房
※この記事は、2016年~2017年に「つくば自然育児の会」会報に連載された「パレオ育児」に加筆修正したものです。