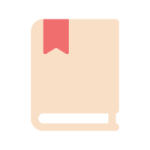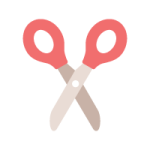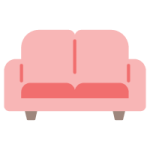ボルネオ島の熱帯雨林で、長年オランウータンの研究をしていた、久世濃子さん。そんな久世さん自身が2児のママになり、見えてきたものとは?サルの研究を通して、「ヒトの子育て」を考える連載です。
この連載では、農耕を開始する以前の社会で、ヒトがどのように暮らし、子育てしていたかを考えています。自然人類学を学んだ筆者が、自身が子育てしながら感じたことや考えたことを書いていますので、しっかりした学術的な根拠(研究論文)がない話も含まれます。「そういう考え方もあるのか~」と気楽な気持ちで読んでいただければ幸いです。
人類進化から見ると、紙の本も電子メディアも違いはない
以前、「人類進化から見て、スマホやパソコンなど、電子メディアとの付き合い方はどう考えたらいいでしょうか?」と質問されたことがあります。
今までの人類の進化の過程では、文字も紙の本も電子メディアも、心や身体の進化に「影響を与えてこなかった」という点では「同じ」です。
人類が直立二足歩行をはじめて、チンパンジーとの共通祖先から袂を分かってから700万年、現生人類ホモ・サピエンスが誕生して20万年の間、99%の時間は、文字も紙も、もちろん電子メディアも存在しませんでした。
そもそも「言語」が誕生したのがいつなのか、もいまだに議論がありますが、少なくとも私たちホモ・サピエンスは、話し言葉(言語)を現代人と同じレベルで操ることができた、と考えられています(ホモ・サピエンスと同時代にヨーロッパに住んでいた、ネアンデルタール人が、ホモ・サピエンスと同レベルの言語能力を持っていたかどうかさえ、現代でも議論があります)。
現代でも「失読症(ディスクレシア)」という特性をもつ人が一定数(人口の3~7%)見られるように、そもそも「言語」能力というのは、非常に複雑です(話す能力、聴く能力、書く能力、読む能力は、それぞれ別個にさまざまな能力の組み合わせから成り立っていて、「平均」から外れた特性を持つ人もいます)。
自然人類学(生物としてのヒトの特性や進化について研究する学問分野)の世界では、言語の進化についてさえ、まだまだ議論が百出しており、電子メディアとの付き合い方を「人類進化」の観点から議論するのは簡単ではありません。
知らない場所にいる子どもも、母親と電話で話すだけで心拍数が下がる
とはいえ、「赤ちゃんは、対面コミュニケーションを通じて、言語能力やコミュニケーション能力を発達させる」ということについては、多くの研究者が同意しています。
一口に電子メディアといっても、いろいろなものがあります。
たとえば、単身赴任中の親や遠方で暮らしている祖父母(親戚)とLINEなどのビデオチャット機能を使って会話するのも、電話も、一種の「電子メディア」です。
一方で、テレビ番組やDVDの視聴なども電子メディアに含まれます。
赤ちゃんが応答できる(相手と相互交渉を持つことができる)「電子メディア」は、赤ちゃんが対面でコミュニケーションをとるのと、大きな違いはない、という報告もあります。たとえば、小さな子どもを初めての場所(部屋)に一人にしたとき、母親の声が聞こえたり、電話で会話できるだけでも、子どもの心拍数が下がる(落ち着く)、という実験結果が報告されています。
一方で、DVDなど、一方的に情報を「受け取る」だけで、赤ちゃんが何らかの行動を起こしても、相手からリアクションがない場合、赤ちゃんのコミュニケーション能力の発達を阻害する、という報告もあります。
要は電子メディアかどうかというより、「相互行為(相互交渉)」が成立するか、情報が一方通行になっているかどうか、が赤ちゃんにとって大きな違いになる、といえるかもしれません。
この続きは「赤ちゃんの相手をするのは、お母さんじゃなくてもいい【コソダテ進化論】」
参考文献
開 一夫 (編集), 齋藤 慈子(編集)(2018)「ベーシック発達心理学」東京大学出版会
岡ノ谷 一夫(著)(2010)「言葉はなぜ生まれたのか」文藝春秋
※この記事は、2016年~2017年に「つくば自然育児の会」会報に連載された「パレオ育児」に加筆修正したものです。