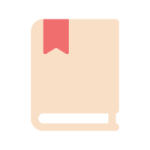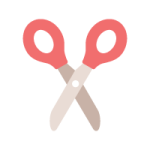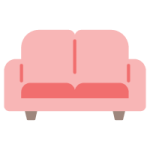今、世界の国々は急いで幼児教育の改革を進めている
前回、早期教育はたいして意味がないということをお話ししました。実は世界の国々が保育とか幼児教育の改革を進めているのですが、それは文字や数という認知的能力(学力がモデル)を早期からというのではなく、もう一つの知的力である非認知的能力を伸ばそうとしているからなのです。
非認知的能力とは何でしょうか?人間の考える営みは、大きく二タイプあります。一つは答えが決まっている問いを考えるということです。正解がある問いを考えるといっていいでしょう。学校の勉強がそのモデルになります。学校の勉強は、これが正しいこと、理解すべきこと、覚えておくべきことという中身が決まっていて、その問いを解く練習を主にしています。その正解度が高い人が「優秀」とされます。
学校と違い、社会では正解のない問いだらけ
それに対して、世の中に出ると、答えが決まっていない問いだらけになります。正解のない問いだらけといってもいいでしょう。会社の売れ行きが落ちている。何等かの原因があるはず。それを解明しなければなりませんが、どこかに正解が落ちているわけではありません。家族でどこに旅行するか、ここにも正解はありません。わが子が不登校に!どう対応すればいいか、正解はやはりなし。
正解のない問いを考えるときは、あれこれ条件を考えて、みんなが最も納得する適切な解を導き出すことが課題になります。そのために懸命に考え、必要に応じて相談し、新たなアイデアを思いつき…という試行錯誤を繰り返さねばなりません。この過程で身につく知的な力、すなわち試行錯誤力やデザイン力、アイデア力、相談力、コミュ力等を、非認知的能力といっているわけです。
大事なことは、社会に出ると認知能力だけでなく非認知的能力の豊かな人がいい仕事をし、人間的にも信頼されていることがわかってきたことです。そこで世界の国々は、この非認知的能力を育てるような教育に大急ぎで変えつつあります。特に乳幼児期には、豊かな遊びの体験が大切になってきたのです。